リハビリテーションの内容
理学療法

また、循環器疾患を有している方には、心臓リハビリテーションを実施しています。
作業療法
「患者様の生活を可能な限り自立へ導き、より安全に、より快適に暮らしていただく」という視点で、主に麻痺が生じた手の専門的なリハビリテーションや、高次脳機能訓練、応用動作練習等を行っています。患者様には日常生活動作(寝起きの動作・食事・身だしなみ・着替え・トイレ・入浴など)や日常生活関連動作(炊事・洗濯・掃除・買い物・外出など)、復職に向けた訓練など、「病院」という環境から「患者様が復帰される環境」を想定しての生活練習までを実践していただきます。
言語療法

「言葉が伝えにくい」「聴いたことが理解しにくくなる」「字が書けない」「計算ができない」など失語症によるコミュニケーションの問題、その他の問題として、口・舌の麻痺が出ることで「呂律が回らない」「声が出にくい」「食事が飲み込みにくい」などの症状が出ることも多くあります。それぞれ患者様の症状にあわせて言葉を理解する・伝える練習や発声発語器官の練習、安全に食べられる形態や姿勢の検討を行っていきます。
急性期リハビリテーション

急性期とは、脳卒中が発症してから1~2週間くらいまでの時期のことです。
脳卒中が発症した後、重大な合併症が出ていなければ入院した日、もしくは翌日にもリハビリテーションを開始します。
急性期のリハビリテーションは「廃用症候群の予防」と、早期からの運動学習による「身の回り動作の早期自立」を最大の目的とします。
重症な方ほど発症直後は様々な管につながれ、麻痺などもあるため御自分で動くことが困難です。そのような方に発症直後から体を起こし、少しでも自力で活動する機会を提供することで、脳が賦活され残存機能の獲得につながります。また、症状が落ち着きリハビリが積極的に行える時期に達した際、非麻痺側の機能が低下しないよう(廃用症候群予防)に努めます。
脳卒中が発症した後、重大な合併症が出ていなければ入院した日、もしくは翌日にもリハビリテーションを開始します。
急性期のリハビリテーションは「廃用症候群の予防」と、早期からの運動学習による「身の回り動作の早期自立」を最大の目的とします。
重症な方ほど発症直後は様々な管につながれ、麻痺などもあるため御自分で動くことが困難です。そのような方に発症直後から体を起こし、少しでも自力で活動する機会を提供することで、脳が賦活され残存機能の獲得につながります。また、症状が落ち着きリハビリが積極的に行える時期に達した際、非麻痺側の機能が低下しないよう(廃用症候群予防)に努めます。
カンファレンス
チームで話し合いリハビリテーションの方向性を決定します。
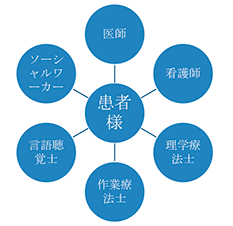
医師、看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、ソーシャルワーカーによるチーム
患者・家族面談
患者さまの現状についてと、カンファレンスで決定したリハビリテーション方針を説明します。